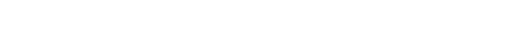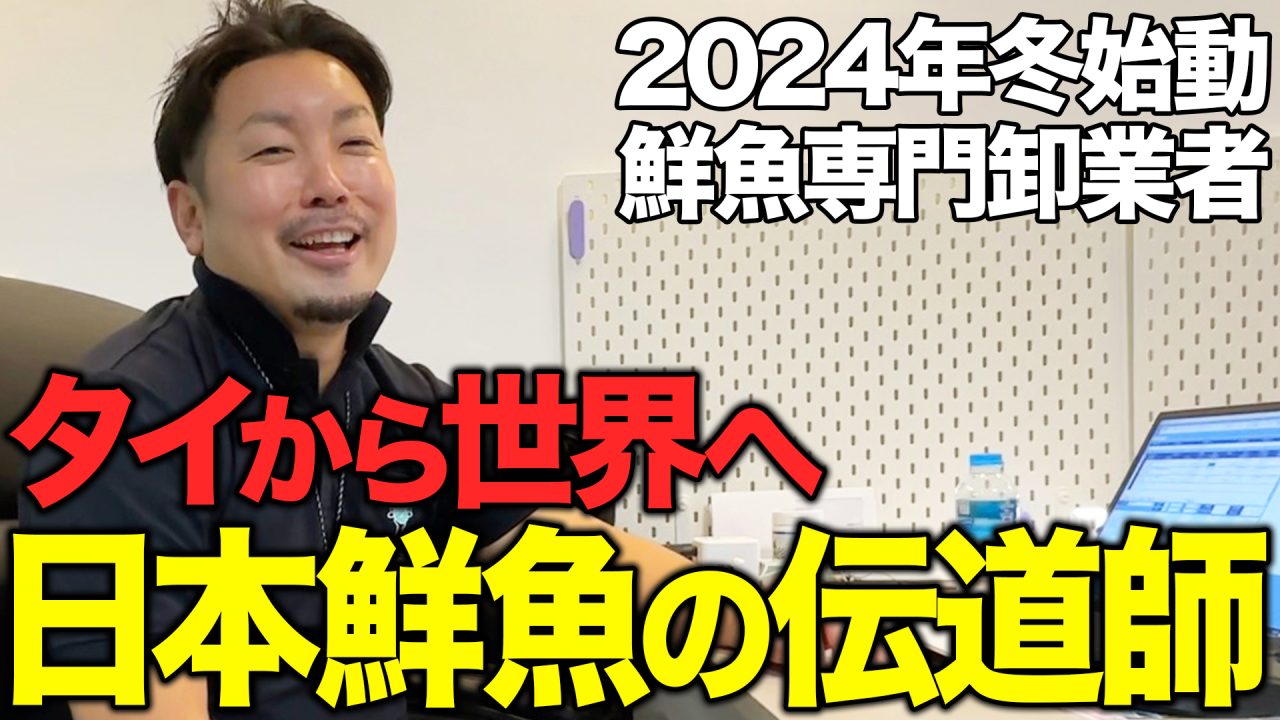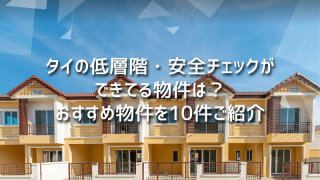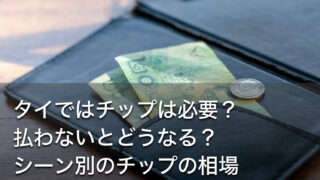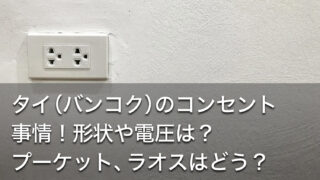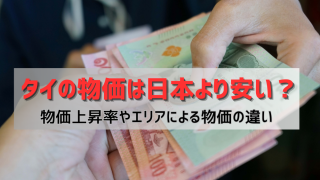ディアライフの季刊誌『Home’s』の2025年度版で取材をさせてもらった馬場さんが、鮮魚専門の卸商社を自身で経営されているということで、誌面だけでなく「タイ駐在チャンネル」のインタビュー企画にも登場していただいた。日本料理ブームのタイであり、同時に日本人居住者も多いバンコクでは「本物」の味が求められるため、鮮魚を日本から運ぶ業者は大切な存在だ。意外と知らない、飲食店の裏方の仕事に迫ってみた。
🍣 日本人増加とタイ人の日本料理ブームで卸の商売が成立

最近のバンコクしか知らない人はごくあたりまえに日本料理店に足を運び、日本の味そのままの料理を楽しんでいるでしょう。ほんの20年前はまだまだ「なんちゃって」な日本料理がほとんどだった。
本格的な日本料理ブームやバンコクの居住日本人が増加したのは2010年前後。それ以前は日本人経営日本料理店はBTSプロンポン駅周辺に数えるほどしかなかったはずだ。ましてや現地採用日本人にはそういった店は高くて、会社の接待や特別な日にしか行けなかったものだ。
その時代の日本料理店経営者は多くが自分で定期的に日本に行って食材を仕入れていた。タイも海に面しているので魚が獲れるので、一部はタイ産の魚で料理をしていたと思う。水温などの違いか、魚は日本で獲れたもののほうがおいしかった。
2010年前後になって日本人が増え、日本料理店も急増。タイ人も日本料理を食べるようになって、ゲテモノ扱いされていた刺身が好まれるようになった。いよいよ鮮魚を専門に扱う商社も商売が成り立つようになったのである。
馬場さんももともとは外資系の鮮魚商社にいた。そして2024年に独立。会社は日本とタイで設立したばかりだが、新卒からこの仕事をしている馬場さんの経験もあって、すでに東京の豊洲市場などから魚を仕入れ、翌日にはバンコクの飲食店に届けるというルートができている。
🐟 魚嫌いが一転して鮮魚の目利きのプロに

馬場さんは学生時代まではむしろ魚が嫌いなくらいだった。それが手伝いをしていた前職の会社の忘年会に呼ばれた際に食べた寿司に感動し、そこから一転して魚好きになった。
もともと就職先として飲食関連を考えていたこともあり、その鮮魚商社に就職し魚のことを徹底的に勉強。今では日本で獲れる魚であればほぼすべての品種の目利きができるという。
一時期、寿司職人の修行年数が話題になった。寿司を握るだけに10年も時間が必要なのか、と。ある寿司職人に話を伺ったところ、確かに握る分にはそこまでの修行は必要ないのだとか。ただ、大切なのは目利きの目を育てることと魚市場の人間関係構築で、それにはそれくらいの時間が必要かもしれない、ということであった。
これは馬場さんにも当てはまることで、バンコクの馬場さんの会社『OTO Foods』は馬場さん自身が常駐する必要があり、日本の市場に毎日顔を出すことができない。
それでもちゃんとした魚が手に入るのは、これまでに懇意にしてきた豊洲の人々から毎日入った魚が画像で送られてくるからだ。
それを基に仕入れる魚を決めて、それを冷蔵でバンコクに持ってくる。翌日の早い時間には馬場さんの手元に魚が届くが、いくら完璧な冷蔵でも日本からは距離があるので、必ず馬場さんがその目で魚の状態を確認。問題がなければ飲食店に届ける。
このため、馬場さんは毎日、早朝から深夜まで働き、睡眠時間はごくわずかだ。それでもおいしいといってくれる消費者の声を励みにがんばっている。
🏠 住まいはやや古いアパートで家族と共に

実は馬場さんのバンコク居住は初めてではない。前職でもバンコク駐在経験があり、再びバンコクに戻ってきた。ちなみに奥さんは馬場さんと知り合うまえにもバンコクにいたことがあり、今回が3回目の移住である。
今回はコンドミニアムではなく、築年数がやや経っている、ちょっとヴィンテージのクラスに入るアパートに住んでいる。
サービスアパートではないので部屋の清掃などのサービスはないものの、アパートなので建物そのものが一括管理されているので、なにかしら不具合があっても解決は早い。
古いアパートというと暗いイメージがあるが、ローカル向けの安いアパートではなく、それなりの所得層向けなので建物そのものの造りはしっかりしている。
そして、バンコクのビンテージ系に共通するように、部屋がゆったりなのがまたいい。ちょっとした戸建て並みの広さがあって、馬場家のようにまだ小さい子どもとの3人暮らしには十分。実際、ほかの入居者も家族世帯が多いようだ。
アパートの計らいもあって、週末には庭に出張販売も来る。ちょっとした日本の食材などを持ってきてくれる業者で、休みの日に買い出しに行く手間も省ける。新興のマンションだとなかなかそういったサービスはないので、馬場さんのいるアパートは人気が高い。
🔑 ディアライフでみつけた住まい
会社設立もあってのタイ移住なので、今回の馬場家の物件探しは初めてディアライフを使ってみた。
ディアライフは日本人駐在員の増加に伴いどんどん売上を伸ばし、企業としての規模もかなり大きくなった。そのため、物件案内や営業、契約、アフターケアとそれぞれ担当者が異なる。
しかし、馬場さんがいうには、内部連携もしっかりしていて、ストレスなく物件をみつけ、入居に至ったそうだ。
馬場さんは土地勘もあったので、エリアや相場などもある程度わかっていたこともあってかなりスムーズに住まいを決められた部分もあるかと思う。
バンコクに来たこともないのに駐在員になるという場合はどこに住んだらいいかわからないかもしれない。しかし今はネットの時代。ディアライフではホームページ、YouTube、季刊誌などで物件の紹介もしているので、それらを参照にしながら決めたら、馬場さんのように好みの物件をみつけられるだろう。
OTO Foods
HP:https://otofoods.com/
IG:@otofoodstagram