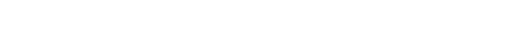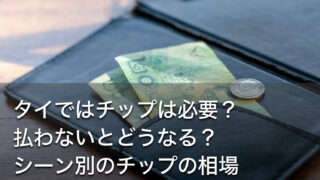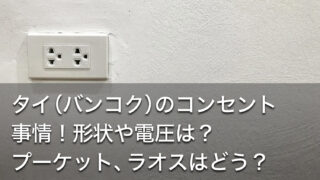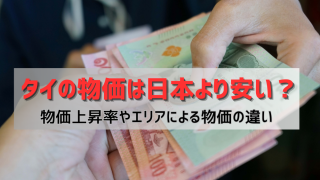タイはムエタイが国技であるものの、タイにおいては純粋なスポーツというよりはギャンブルとして主に男性に好まれる。2024年後半にタイではギャンブルの規制がかなり緩和されたが、そもそもムエタイは認可された競技場では合法だった。同時に鶏を使う「闘鶏」もまた昔からある賭けごとであり、タイ国内に闘鶏場が1000か所はあるとされ、公認のギャンブルとして人気がある。そんなタイ闘鶏に関わるプムさんの家を訪問した。
タイの闘鶏の歴史
闘鶏はタイに限らず世界中にあり、古いところでは紀元前からあるとされる。タイも数百年まえにはすでにあったとされ、一説ではアユタヤ王朝のナレースワン王がはじめたものという。
タイ闘鶏で使われる鶏は筋肉質で大型だ。この鶏は日本にも入っていて、日本では地鶏の一種として食用される。「軍鶏」と当て字される鶏で、タイの旧名であるサイアムが日本風に訛った「シャモ」と読む。
タイでは闘鶏もムエタイ同様に「文化」として認められていて、公認競技場では賭けをすることが許されている。そこではアマチュアからプロがいて、賞金も数千バーツ程度の試合もあれば、数万バーツから100万バーツなどの大きな試合もある。
闘鶏にはさまざまな関わり方、あるいは稼ぎ方があって、ギャンブルで稼ぐ人もいれば、プムさんのように飼育・トレーニングをして出場したり、鶏を売買する。勝てば1羽数万バーツ、チャンピオンだとかつては1000万バーツにもなったそうだ。
ただ、人間と違うので、一度負けてしまうと闘志を失い、闘鶏には使えない。エサも特殊なので食用にはならず、競走馬が引退後は種馬になるように、子どもの繁殖に利用されるのだとか。ある程度実績のある鶏のひよこであれば数千バーツで売れるそうだが、チャンピオンの子どもが強くなるという科学的な根拠はないらしい。
闘鶏の賭け方はムエタイとほぼ同じ
 OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERAタイの闘鶏は会場によってルールが異なる。1試合20~25分が一般的で、国によっては脚に刃物をつけて闘わせるそうだが、タイでは爪などにはテープを巻き、致命傷を与えないという仏教国らしいルールがある。それでも軍鶏はかなり大きいので、飛びあがっては蹴りあう姿はなかなか迫力がある。
タイでの賭け方はムエタイとほとんど同じだ。「負けたら1万やるから、勝ったら5000くれ」というような合図を手の形で出し(タイでは2-1という数字の合図を出す)、会場にいる人同士で賭ける。つまり胴元がいない。慣れた人は負けそうな雰囲気になると、株式売買のような反対オファーを出し、損失を最小限に食い止めるというテクニックを使う。
結局のところ、相手があっての賭けごとであり、ごく稀に金がなくて払えないというトラブルも起こる。ベテランは先のように反対売買もしているので、そんなことをしては身動きが取れない。というわけで、ムエタイ同様に基本的には顔見知りと賭けをすることが普通だ。
よく観光でタイに来た人がムエタイ・ギャンブルをしてみたいというが、それは無理だ。よそ者は相手にしてくれないし、そもそも取り引きを成立させるための指の形など初心者には難しい。ちなみに賭け金を払えなかった場合に暴行を受けることがあるが、その際に駆けつける警察などが捕まえるのは払えなかったほうである。
トレーニングにもコツがいる
 OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERAタイ闘鶏の勝敗判定は、相手から逃げるそぶりをするか、地面に伏せて降伏した場合になる。つまり、戦意喪失が見られたら、ということになるが、ムエタイと違うのは明らかにそれと見られない限りは引き分けとされ、賭けも不成立になることだ。動物なので、やや曖昧な部分がある。
プムさんは取材時18羽の鶏を飼っていた。気が荒い鶏なので、2羽を一緒に檻に入れることができないので、養鶏場の飼い方とは大きく異なる。エサや毛並みの手入れなども同様だ。さらに、闘う筋肉を育てるためにジャンプ力をつける筒を造ったり、さまざまなノウハウを駆使する。
プムさんはすでにたくさんの実績を残していて、タイ全土から注文が入る。また、実戦でも賞金を稼いでいて、これまでに20万バーツ以上は儲けた。東北部の農村なので物価も高くないため、1000バーツ札が日本の1万円札くらいの価値観になる。となると、200万円くらいともいえるので、なかなかの賞金だ。
鶏も取材時にいたもので5万バーツくらいの値がつくものもあったり。飼育費用は月あたりかかって数百バーツ。一般的には10か月で十分戦えるサイズになるので、鶏そのものの売買でも十分に利益を得ることは可能だ。
タイの闘鶏にはほかにもエサの開発、病気対策のクスリなどもあって、いろいろな関わり方がある。確かに、ひとつのタイ文化として成立しているともいえる。
さすがに都心では飼えない?
日本人でもタイ闘鶏のビジネスに興味がある人もいるかもしれない。とはいえ、プムさんのように農村の広い家がないと飼育は困難なのだろうか。プムさんはすぐに異変に気がつけるよう、鶏小屋の横で寝ている。家族とは別々の家に住んでいるのだ。
実際的には1羽2羽程度ならバンコク都内でも飼える。トンローのセンセーブ運河寄りの、昔からこの地域に住む人たちの住宅街では鶏を飼う世帯も散見されるので間違いない。トレーニングにはある程度の知識と広さがいるものの、飼うだけなら不可能ではない。
とはいえ、ディアライフが扱う賃貸物件では難しい。ディアライフが扱うのはコンドミニアムが基本で、さすがに一軒家などでないと世話はできない。そもそもペット不可の部屋もあるし、OKであったとしてもそれはイヌかネコを前提にしていることが大半なので、闘鶏はそれ用の物件を探すしかない。